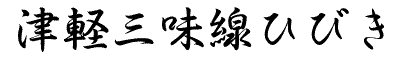津軽三味線の魅力
昨年、二人の若い兄弟がメディアに登場してからというもの、東京を中心にして津軽三味線のブームが若者の間で新しい楽器として全国に広がりかけている。
津軽三味線の由来は16世紀に遡り、琉球(今の沖繩)から伝わったとされている。
沖繩には今でもヘビ皮を張った蛇味線が使われている。それが琵琶法師によって改造され、現在の形となり、琵琶のように大きな撥でひくのが日本の特長です。
三味線には大きく分けて三種類あり、棹の太さ、たいこの大きさ、糸の太さが異なり、棹には、細ざお、中ざお、太ざおとがあり、細ざおは長唄や小唄、中ざおは地唄、ときわずや清元、太ざおは義太夫とその音楽によって使い分けられている。
津軽三味線は太ざおの義太夫三味線をもう少し太くし、たいこも大きくし、少しずつ改良され、今の形になったとされる。
今の形になってまだ百年足らずと、歴史は浅いが、三味線を弾く技法は、すごい勢いで進化し続けている。
その昔、テレビもラジオもなかった時代に、人々が口ずさむ唄といえば、わらべ唄や民謡、または小唄や長唄であった。
このような唄には三味線や尺八などの伴奏は必要不可欠でまさに音を楽しむ“楽器”であった。しかし津軽での三味線などの楽器は食べていくだけの“道具”でしかなかった。
そのほとんどが農家であった津軽で三味線を持たなければならないということは何を意味していたか。
五体満足なら、多少勉強ができなくても農業はできる。でももし目が不自由なら、出来る仕事と言えば、マッサージ師であった。それも出来ない者は、ぼろぼろの三味線を抱き、一軒ずつ家を廻り、物を貰って生活をしていた(門付け芸人)。だから一般の家庭で、三味線を習いたいなどと言ったものなら「あんな物貰いみたいな事をするなら勘当だ」とまで言われた時代であった。
杖(ぼう)をつき、あるいは家族の者に杖(ぼう)で導かれ門付けをしている人達を人々はぼさま(ぼうさま)と呼んでいた。
ある時はぼさまを見かけると子供達はからかい、さらには石を投げる者さえいた。
それでも生きていく為にこのように門付けをしながら細々と暮らしていた。そうこうしているうちに目の不自由なぼさま達にもかすかな光が射したのは蝦夷地(今の北海道)の開拓というものであった。その開拓には多くの津軽の人々が出稼ぎに来て何ヶ月もの間、故郷へ帰れず、寂しい思いでいる人々の心をなごませたのが同じく蝦夷地へ渡ったぼさまが弾く三味線と津軽民謡であった。
そうして蝦夷地という舞台があり、そこでドサ廻りする一座から、故初代木田林松栄や故初代白川軍八郎などのいわゆるスターと呼ばれる存在が現れ始めた。
その後、みなさんも御存知の高橋竹山が現れるが竹山も目の不自由な門付け芸人であった。
そこで忘れてはならない事は、今の津軽三味線というものがあるのも、やぶれた着物とおんぼろの三味線で、ある時は石まで投げられながら門付けをし続けたぼさま達がいたからだと私は思います。
三味線を弾く技法もさることながら、三味線や撥の素材も少しずつ改良されていった。
棹は反ったり捩じれたりしない固い木を選び、花梨や黒檀などが使われていた今は主に紅木(コーキ)が使われている。
糸巻きは紫檀や黒檀を使う。又象牙は高価ではあるが見栄えもよく巻き戻りも少ない。撥は昔、ほとんどが黄楊の木を使っていたが、すぐに先が減るので削りととのえながら使っていた。今は弾き方も弾くというより叩くので弾力がありながら折れにくい亀甲が主流となっている。
次ぎに皮の話に移りたいのですが、これを書いている私も三味線を弾き、そして三味線の命ともいえる皮も自ら張っていますが、昔は猫の皮だったのが長唄三味線を除いて今はほとんど犬の皮を使用している。胴(たいこ)も大きな津軽三味線は皮も大型犬の厚い物を使いパンパンに張ることにより、カンカーンと響くいい音が出るのです。でも本当は皮の張り具合によって撥の厚み、駒や糸の太さも変えるべきだと思います。
最後に私は京都生まれで今は大阪に住んでいますが、京都弁を津軽の人が喋れないのと同じであの津軽のテンポと間はやはり津軽の人でしか出せないのではと私はそう思いつつ今日も津軽三味線を弾いています。
(川合絃生、平成13年3月記)